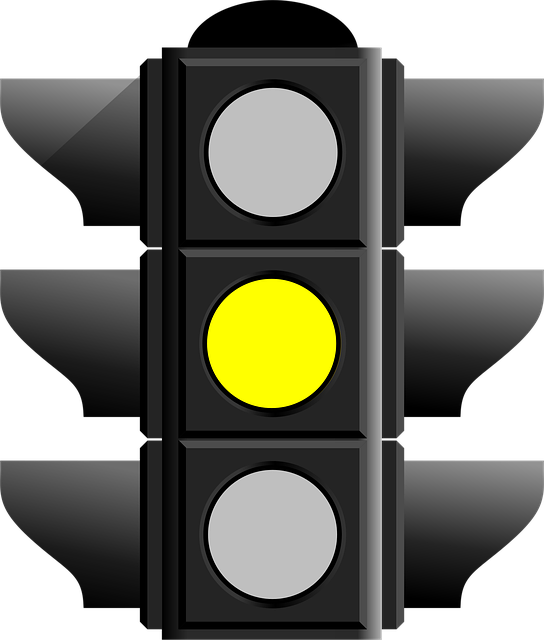新NISAが始まり、「高配当株」への投資で安定したインカム(分配金)を得たいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に楽天証券などの金融機関で商品を探してみると、「つみたて投資枠で買いたいのに、高配当株ファンドが見つからない」と疑問に思われるかもしれません。
この記事では、新NISAの枠組みと高配当株ファンドの関係性、そして人気の米国高配当株ファンド(VYM連動)と王道のS&P500について、過去の事実に基づき徹底的に比較・解説します。
新NISA「つみたて投資枠」で高配当株ファンドは買いにくい?
まず結論から申し上げますと、新NISAの「つみたて投資枠」で購入できる高配当株インデックスファンドは、非常に限られています。
理由:「つみたて投資枠」の対象基準
「つみたて投資枠」で購入できる投資信託は、金融庁が定めた「長期の積立・分散投資に適した」基準を満たす必要があります。
これは主に、S&P500や全世界株式(オール・カントリー)のように、特定の市場全体に幅広く分散投資するインデックスファンドが中心です。
一方で、「高配当株」というテーマに絞ったファンドは、投資対象が限定されるため、この「幅広く分散」という基準を満たしにくく、多くが「つみたて投資枠」の対象外となっています。
解決策:「成長投資枠」の活用
高配当株ファンドに投資したい場合の主な選択肢は、新NISAの「成長投資枠」を活用することです。
「成長投資枠」であれば、金融庁の基準を満たした「つみたて投資枠」対象ファンドはもちろん、より幅広い投資信託やETF(上場投資信託)を選ぶことが可能になります。
【成長投資枠】人気の米国高配当株ファンド徹底比較
「成長投資枠」で購入できる米国高配当株ファンドとして、特に人気が高いのが、米国のバンガード社が運用する**「VYM(バンガード・米国高配当株式ETF)」**に連動する投資信託です。
VYMは、米国の高配当利回りの銘柄で構成される「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」に連動し、分散が効いている点と経費率の低さが魅力です。
楽天証券では、このVYMに実質的に投資できるファンドとして、主に以下の2つが挙げられます。
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・VYM)
- SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・米国高配当株式)
どちらも同じ「VYM」を投資対象としているため、投資成果(値動き)はほぼ同じになります。したがって、選択の決め手となるのは**「運用コスト(信託報酬)」と「ファンドの規模(純資産総額)」**です。
事実に基づく比較表(2025年10月時点のデータに基づく)
| 項目 | 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 | SBIアセットマネジメント |
| 信託報酬 (年率・税込) | 0.192% | 約0.1238% |
| (内訳:ファンド報酬) | 0.132% | 約0.0638% |
| (内訳:投資対象ETF経費率) | 0.06% | 0.06% |
| 純資産総額 | 約288億円 | 約340億円 |
| 設定日 | 2018年7月 | 2021年6月 |
| NISA枠 | 成長投資枠 | 成長投資枠 |
どちらを選ぶべきか?
上記の事実から、以下のことが言えます。
- コスト重視なら「SBI」投資対象が同じである以上、運用にかかるコスト(信託報酬)は低い方が合理的です。「SBI・V・米国高配当株式」は、楽天のファンドよりも低い信託報酬を提供しています。
- ファンドの規模・人気なら「SBI」純資産総額は、そのファンドにどれだけのお金が集まっているか(人気や安定性)を示す指標です。後発ながら、「SBI・V・米国高配当株式」が純資産総額でも上回っている状況です。
したがって、特別な理由がなければ、コストが低く純資産総額も大きい「SBI・V・米国高配T当株式インデックス・ファンド」を選ぶのが合理的な判断と言えるでしょう。
【10年実績比較】VYM(高配当株) vs VOO(S&P500)
では、投資対象である「VYM(高配当株)」は、王道の「S&P500(VOOなどのETF)」と比較して、過去10年間の実績はどうだったのでしょうか。
※データは2015年~2025年の概算値に基づき、分配金を再投資した「トータルリターン」で比較しています。
| 項目 | VYM (米国高配当株) | VOO (S&P500) | ポイント解説 |
| トータルリターン (年率) | 約11.6% | 約14.1% | 過去10年はS&P500がリターンで上回りました。 |
| トータルリターン (累計) | 約197% (約2.97倍) | 約274% (約3.74倍) | 10年前に投資した資金の増加率です。 |
| 平均分配利回り | 約3.0% | 約1.8% | VYMはS&P500より高い分配金を提供しました。 |
| 下落耐性 (例:コロナショック時) | 比較的小さい | 比較的大きい | VYMは不況に強い銘柄構成のため、下落幅が抑えられる傾向がありました。 |
分析:何を重視するかで選択が変わる
過去10年の実績は、将来の資産価値の最大化(トータルリターン)を目指す上では、S&P500(VOO)の方が優位だったことを示しています。これは、GAFAMなどのハイテク企業が市場全体を強力に牽引した結果です。
一方で、VYMの強みは以下の2点です。
- 高い分配金(インカム): 株価が上がりにくい時期でも、S&P500より高い分配金がリターンを下支えします。
- 下落耐性(ディフェンシブ性): 市場の暴落局面において、S&P500より下落幅が小さい傾向があり、精神的な安定につながる可能性があります。
結論:S&P500に追加投資する、という選択の合理性
もし、すでにS&P500や全世界株式(オール・カントリー)といった「コア資産」に投資されている方が、余剰資金で高配当株ファンドを追加投資すべきか迷った場合、どう考えればよいでしょうか。
選択肢は2つあります。
- 「VYM連動ファンド」を追加し、ポートフォリオの安定性や分配金を強化する。
- あえて投資先を増やさず、「S&P500」に追加投資(買い増し)する。
ここで、2番目の「S&P500に買い増す」という選択の合理性について触れておきます。
- トータルリターンの追求: 過去の実績が示す通り、将来の資産価値の最大化を最優先するならば、S&P500に集中投資を続けることは目的に適っています。
- シンプルさの強み: 投資先をシンプルに保つことで、資産管理が容易になり、「長期的に投資を継続する」という最も重要な行動を迷いなく実行できます。
- コア資産の強化: 新しい種類の資産に分散するのではなく、最も信頼する「幹」となる資産をさらに太くしていく、王道の戦略です。
まとめ
高配当株投資は魅力的ですが、新NISAの「つみたて投資枠」では選択肢が限られます。「成長投資枠」を活用する必要があり、その際は「SBI・V・米国高配当株式」がコスト面で有力な候補となります。
ただし、過去10年の実績では、トータルリターンはS&P500が上回りました。ご自身の投資目的が「将来の資産最大化」なのか、それとも「定期的な分配金や安定性」なのかを明確にし、最適な投資判断をすることが重要です。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品を推奨するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。