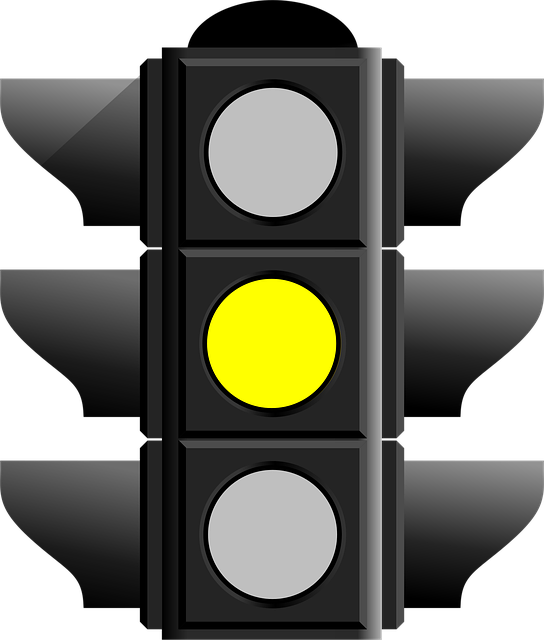2024年から始まった新しいNISA制度では、「1,800万円」という数字が大きな注目を集めています。
本記事では、「1,800万円までとはどういう意味か」「投資戦略として売却と買付をどう使うべきか」など、NISAを最大限に活用するための考え方を丁寧に解説いたします。
新NISAの「1,800万円」とは?生涯非課税保有限度額の仕組み
新しいNISAでは、「生涯非課税保有限度額」が最大1,800万円と定められています。これは投資元本(買付額ベース)で非課税のまま保有できる上限額です。
- つみたて投資枠:最大1,800万円まで
- 成長投資枠:このうち1,200万円まで
- 両者を合計して最大1,800万円の投資元本を非課税で保有可能
非課税保有限度額の考え方
この「1,800万円」というのは評価額ではなく、累計の買付金額です。したがって、以下のようなポイントに注意が必要です。
- 評価額が値上がりして2,000万円になっても、非課税扱いは継続
- 値下がりしても、使った投資枠は戻らない
- 売却すれば、その取得価額(元本)分だけ翌年以降に枠が復活する
年間の買付上限は360万円まで
制度上は年間に購入できる金額にも上限があります。
- つみたて投資枠:年間120万円まで
- 成長投資枠:年間240万円まで
- 合計:年間360万円まで非課税で購入可能
この年間上限を意識しながら計画的に積み立てることが、NISAを最大限に活用するポイントです。
年60万円の積立なら、30年で1,800万円に到達
たとえば、つみたて投資枠で年間60万円を積み立てた場合、1,800万円に到達するまでには30年かかる計算になります。
60万円 × 30年 = 1,800万円
このように、売却しないまま積立を継続すると、いずれ非課税枠を使い切ることになります。
非課税枠を“リセット”して再活用することは可能?
NISAの戦略として、「1,800万円に達したら売却し、また0からスタートする」という方法も理論上可能です。
具体的な流れ
- 評価益が出たタイミングで非課税のまま売却
- 取得価額分の枠が、翌年の1月1日に復活
- 復活した枠を使って、翌年以降また買付を再開
ただし、注意すべき点があります。
- 枠が復活するのは「翌年」から(同じ年には再投資できない)
- 復活するのは「取得価額ベース」であり、売却益は含まれない
- 年間360万円の買付上限は変わらないため、枠の再利用には時間がかかる
売却と買付を並行させる「ロール運用」が現実的
1,800万円に到達したあと、計画的に売却と買付を並行(ロール)する運用で、非課税枠を維持し続けることも可能です。
運用例:毎年360万円ずつローテーション
- A年:360万円を新規買付(合計で1,800万円に到達)
- B年:保有のみ(新規買付不可)
- C年:取得価額360万円分を売却 → 翌年枠が復活
- D年:再び360万円を新規買付
このように、「取得価額分だけ売却 → 翌年その枠を再利用」を毎年繰り返すことで、非課税運用の期間を延ばし続けることが可能です。
メリットと注意点
| 項目 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 税金ゼロで利益確定 | 非課税で売却できる | 翌年まで枠は再利用不可 |
| 枠を永続的に維持 | 理論上、一生涯使える | 再投資には資金余力が必要 |
| リバランスがしやすい | 売却を計画的に行える | タイミングによっては機会損失あり |
まとめ:NISAの「1,800万円」はゴールではなく、活用戦略の起点
新NISAの「1,800万円」という非課税保有限度額は、制度の上限ではありますが、投資を終えるラインではありません。
むしろ、「どのようにしてこの枠を有効に使い続けるか」を考えることが、長期資産形成において重要です。
売却と買付を計画的に並走させ、非課税枠を活かし続けることで、資産運用の効率を最大化することが可能です。
新NISAの制度を正しく理解し、ご自身に合ったペースで活用していきましょう。
投資の勉強、書籍代がかさみませんか?

ここまで読んでいただきありがとうございます。最後に宣伝をさせてください。
株式投資、NISA、不動産投資など、お金の知識を深めようとすると、1冊1,500円以上する専門書が何冊も必要になります。
Kindle Unlimitedなら、月額980円で500万冊以上が読み放題。ベストセラーの投資本や節約術の本も多数対象になっています。1冊読むだけで元が取れる計算ですが、今なら「3ヶ月499円」という破格のキャンペーンが表示される可能性があります。まずはご自身が対象か、下記よりチェックしてみてください。