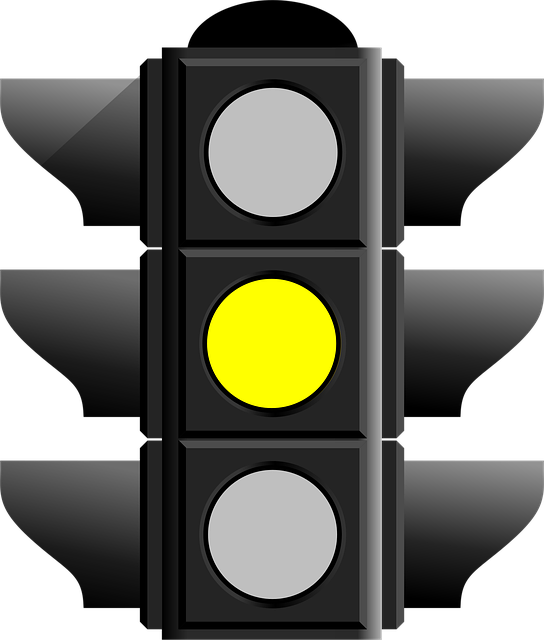~トラス政権の経済政策とその教訓、日本の対応のあり方を考える~
はじめに
2022年、イギリスではリズ・トラス元首相による大規模な減税政策が導入されましたが、その結果として金融市場が混乱し、政権はわずか45日という短命に終わりました。日本でも近年「減税」への関心が高まる中、このイギリスの事例がしばしば引き合いに出されています。しかし、両国の経済環境は大きく異なります。本記事では、イギリスの減税政策の内容と失敗の要因を詳しく解説し、日本との違いについて考察いたします。
トラス政権の減税政策とは?具体的な内容と失敗の背景
リズ・トラス政権が2022年9月に発表した「ミニ・バジェット」と呼ばれる経済政策は、以下のような大規模な減税を柱として構成されていました。
主な減税内容(ミニ・バジェット)
- 所得税の基本税率の引き下げ
20%から19%へ。2024年に予定されていた変更を前倒しで実施。 - 高額所得者向け追加税率(45%)の廃止
年間15万ポンド以上の所得に対して適用されていた最高税率の撤廃。 - 法人税の引き上げ撤回
19%から25%への引き上げを中止し、現行の19%を維持。 - 国民保険料(National Insurance)の引き下げ
2022年4月に導入された1.25%の引き上げを撤回。 - 健康・社会保障税(Health and Social Care Levy)の廃止
- オフペイロール労働に関するIR35改革の撤回
- 印紙税(Stamp Duty)の引き下げ
免税枠を引き上げ(一般購入者:25万ポンド、初回購入者:42.5万ポンド)。 - 企業投資控除額の恒久化
年間控除枠を100万ポンドに。 - 従業員株式オプション制度の上限引き上げ
3万ポンドから6万ポンドに。 - 銀行家のボーナス上限の撤廃
- 非居住者向けのVAT(付加価値税)免税制度の新設
- 酒類税の凍結
これらの減税策はいずれも供給側経済学(サプライサイド経済学)に基づき、経済活性化を目的としていましたが、財源の確保が不十分であり、かつ市場との調整も不在だったため、信頼を著しく損なう結果となりました。
失敗の影響:金融市場の混乱と政権崩壊
政策発表直後から金融市場は大きく反応し、以下のような現象が立て続けに起きました。
- ポンドの急落
- 英国債の利回り急騰
- 株価の下落
- 住宅ローン市場の混乱
これにより「トリプル安」が発生し、政権は火消しに追われ、最終的には多くの政策を撤回せざるを得なくなりました。リズ・トラス氏自身も辞任を余儀なくされ、英国史上最短の在任期間となりました。
日本との違い:イギリスと同じ轍は踏むのか?
日本においても、最近では減税の必要性が議論されています。実際、一部の政治家からは「イギリスのような失敗を避けるべき」という慎重論も聞かれますが、日本とイギリスの経済状況は本質的に異なるため、単純な比較は適切ではありません。
日本とイギリスの違い(主なポイント)
| 観点 | イギリス | 日本 |
|---|---|---|
| インフレ率 | 約10%(当時) | 2~3%前後(2025年時点) |
| 財政赤字の扱い | 市場からの信頼が低下しやすい | 国債は主に国内で保有、信頼性が高い |
| 対外純資産 | 比較的低い | 世界最大の純資産保有国 |
| 市場との対話 | 突然の政策で混乱を招いた | 政策実施前に丁寧な調整が行われる傾向 |
| 財源の裏付け | 不十分なまま減税断行 | 財源確保を前提とした施策が多い |
このように、日本はインフレも穏やかで、財政規律に対する信頼性も比較的高く、減税実施のハードルはイギリスよりも低いと評価される側面があります。ただし、油断は禁物であり、イギリスの教訓を参考にしながら、慎重かつ段階的な減税政策が求められます。
おわりに:イギリスの教訓から得られるもの
リズ・トラス政権の失敗は、財源の裏付けを欠いた急激な減税政策が、いかに市場の信頼を損なうかということを如実に示した事例です。日本も減税を検討するのであれば、政策の透明性、財源の確保、市場との丁寧な対話が不可欠です。
一見似ているようで根本的に異なる両国の事情を正しく理解し、短期的な人気取りに終わらない、持続可能な政策運営を期待したいところです。
投資の勉強、書籍代がかさみませんか?

ここまで読んでいただきありがとうございます。最後に宣伝をさせてください。
株式投資、NISA、不動産投資など、お金の知識を深めようとすると、1冊1,500円以上する専門書が何冊も必要になります。
Kindle Unlimitedなら、月額980円で500万冊以上が読み放題。ベストセラーの投資本や節約術の本も多数対象になっています。1冊読むだけで元が取れる計算ですが、今なら「3ヶ月499円」という破格のキャンペーンが表示される可能性があります。まずはご自身が対象か、下記よりチェックしてみてください。