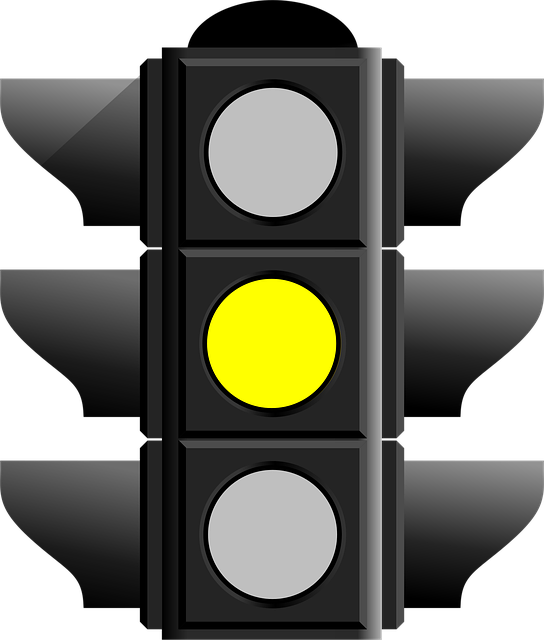インデックス投資とは
インデックスとは、英語で「索引」「見出し」「指数」「指標」などの意味を持つ言葉です。
投資の世界におけるインデックスは「指数」という意味で使われ、
米国株でいえば、NYダウ、S&P500、ナスダック総合指数などが代表例です。
このような株価指数(インデックス)に連動する運用を目指すのがインデックス投資、またはパッシブ投資と呼ばれています。
インデックス投資は、特定の指数に沿った運用を行うため、
企業分析や情報収集にかかるコストや人員が最小限に抑えられています。
そのため、アクティブファンドと比較して、手数料が安いのが大きな特徴です。
株式投資というと、通常はトヨタやアマゾンなど、個別企業の株式を売買するイメージがあります。
一方でインデックス投資は、たとえばS&P500に連動する商品であれば、S&P500に採用されているすべての企業に分散投資しているのと同じ効果が得られます。
個別株投資では、企業の財務情報や業績の分析、将来予測など、頻繁な情報チェックが求められますが、
インデックス投資であれば、一度購入してしまえば、あとは定期的に価格を確認する程度で済むため、非常に手間がかかりません。
多忙な現代人にとって、「楽に、着実に投資できる」という点が、インデックス投資の魅力となっています。
効率的市場仮説とインデックス投資
インデックス投資は、「効率的市場仮説(EMH)」を背景に広まった投資手法です。
効率的市場仮説とは、
「市場価格にはあらゆる情報がすでに織り込まれており、特定の銘柄選定やタイミング投資で市場平均を上回ることは難しい」
という考え方です。
この仮説のポイントは以下のとおりです。
- 株価はすでにすべての情報を反映しているため、市場平均を上回る運用は困難
- 売買のタイミングを図っても安定的に儲けることはできない
この理論に基づけば、
プロのファンドマネージャーによるアクティブ運用よりも、
市場平均に連動するインデックスファンドの方が効率的かつ堅実だと考えられます。
なお、効率的市場仮説には賛否両論があり、完全に証明されたわけではありませんが、
この考え方が、インデックスファンドやETF(上場投資信託)の普及を後押ししてきた事実は間違いありません。
アクティブ運用は長期では不利
アクティブ運用とは、ファンドマネージャーが独自に銘柄を選定し、
市場平均を上回る成果を目指して運用するスタイルです。
たとえば、米国市場のS&P500をベンチマークとするアクティブファンドであれば、
S&P500以上のリターンを目指して、より成長が見込める企業を積極的に選びます。
しかしながら、アクティブ運用には次のような課題があります。
- 運用にかかる手数料(信託報酬など)が高い
- 選定ミスや市場予測の失敗リスクがある
実際に統計データを見ると、
- 運用期間1年で、69%以上のアクティブファンドがインデックスファンドに敗北
- 運用期間15年で、89%以上のアクティブファンドがインデックスファンドに敗北
という結果が報告されています。
つまり、長期投資になればなるほど、アクティブ運用は市場平均に勝てない確率が高いのです。
まとめ
このような背景から、インデックス投資は以下の理由で人気となっています。
- 手数料が安く、手間がかからない
- 分散投資が簡単にできる
- 長期的に安定した成績が期待できる
- 専門知識がなくても取り組みやすい
私自身も、バンガード社の商品を利用して、毎月コツコツ積立投資を行っています。
「インデックス投資は退屈だ」と言う方もいますが、
私は、着実に資産を積み上げることを目指して、
これからも焦らず、地道にインデックス投資を続けていくつもりです。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。