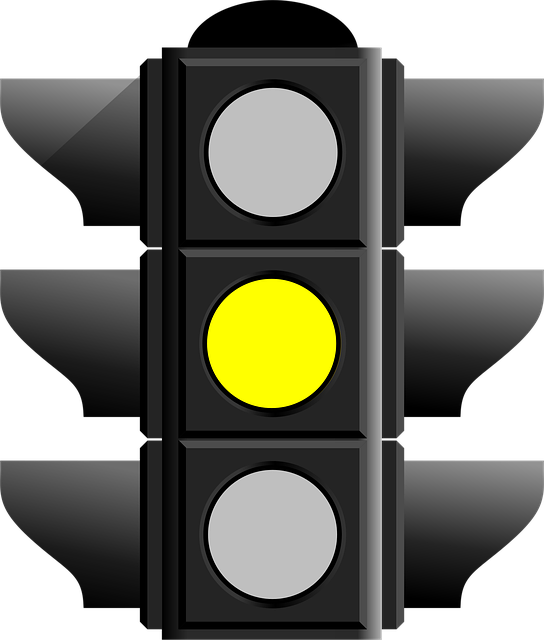証券マンとは何者か
最近、証券会社の方からお話を伺う機会がありました。
その内容は、非常に辛辣で、金融業界の裏側を垣間見るものでした。
ここでは、そのお話を整理しながら、証券マンの実態についてまとめてみたいと思います。
証券マンの仕事は「商品を売ること」
証券マンは、相場のプロフェッショナルでも、コンサルタントでも、評論家でもありません。
あくまで「自社商品を販売すること」が業務の中心であり、普通のサラリーマンです。
仮に、顧客から「お金がない」と相談を受けた場合、
その顧客が保有している株式、金、投資信託などを売却させ、現金化させたうえで、新たな商品を買わせるという手法を取ることもあります。
また、無理にリスク資産の売買を繰り返させ、売買手数料を稼ぐというビジネスモデルも存在します。
被災者は「良い顧客」とされる現実
心地よい話ではありませんが、被災者は生命保険金などで一時的に多額の現金を保有するため、
証券会社にとっては「良い顧客」とみなされることもあります。
通常、生命保険金は銀行に預金されます。
これを証券会社は、「国債」など、より金利の高い商品への乗り換えを提案します。
銀行預金の低金利と比較し、国債のほうがやや有利なため、顧客にとっても悪い話ではありません。
しかし、これはあくまで「入り口」に過ぎません。
一度、国債を購入してもらうと、その後、
- 償還時
- 中途解約時
に再び証券会社がアプローチし、
投資信託などのリスク資産に資金を移すという流れに持ち込みます。
この一連のプロセスの中で、売買手数料が発生し、証券会社が利益を上げる仕組みとなっています。
そのため、国債販売時には、銀行以上に大胆なキャンペーンを展開するケースが多く見られます。
証券マンが抱える苦悩
もちろん、すべての証券マンが無神経に営業をしているわけではありません。
中には、
- 顧客の大切な資産が目減りする姿を目の当たりにしたとき
- その手数料で自身が生計を立てていると自覚したとき
強い罪悪感に苛まれ、業界を去る人もいるといいます。
また、証券会社が取り扱う有価証券の中には、
市場に流通しているものだけでなく、国や企業などが発行する新規発行証券も含まれます。
これらは引き受け販売を義務付けられるため、
中には「質の低い商品(ゴミ商品)」を顧客に勧めなければならない場面も存在します。
「ものづくり大国日本」と金融の関係
大手インフラ企業、メーカー、通信会社など、多くの日本企業は、
証券会社を通じて資金調達を行っています。
国や地方公共団体も同様です。
これにより、集めた資金でインフラ整備や製造業の発展が支えられ、
社会全体の成長につながっています。
金融業界はしばしば「虚業」「詐欺まがい」と批判されることもありますが、
どの業界にも負の側面は存在します。
一方的に証券マンを嫌ったり、軽蔑したりするのは、
金融の本質を見誤ることにもなりかねません。
私自身、この話を聞いて、
金融の世界もまた必要不可欠な社会インフラであると感じました。
まとめ|金融業界の裏側を知り、自衛する
証券マンの実態を知ることは、投資家にとっても大切な学びです。
- 証券会社は、あくまでビジネスとして金融商品を販売している
- 顧客の利益と必ずしも一致しているわけではない
- 自ら学び、判断できる力が必要
このような認識を持ったうえで、
金融機関と適切な距離感を保ちながら、資産運用に取り組んでいきたいと考えています。