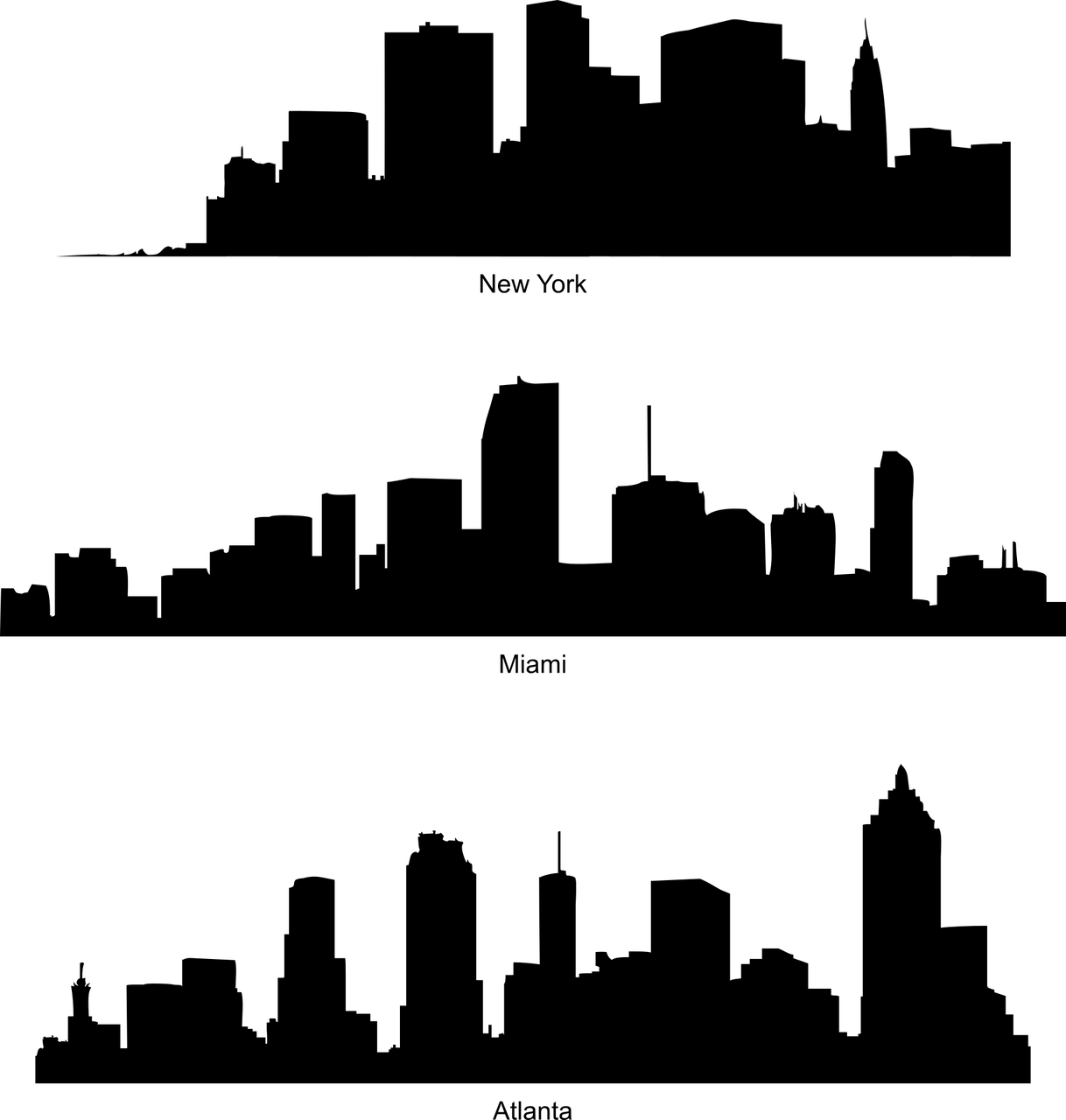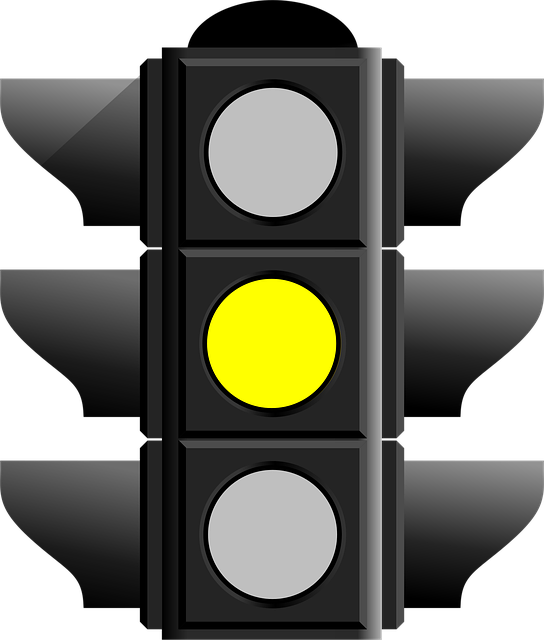QQQに興味を持ったきっかけ
ETF関連の本を読み進める中で、**パワーシェアーズ QQQ(ティッカー:QQQ)**という印象的な名前に惹かれ、今回詳しく調べてみました。
QQQは、主に米国ハイテク企業を中心に構成されるナスダック100指数に連動するETFです。
ハイテク・IT分野に興味のある私にとって、非常に気になる商品でした。
QQQ(パワーシェアーズ QQQ信託シリーズ1)の概要
QQQは、
ナスダック100指数(Nasdaq-100 Index)に連動する投資成果を目指すユニット型投資信託です。
この指数は、コンピュータハードウェア・ソフトウェア、通信、小売、バイオテクノロジーなど、
幅広い業界の主要企業によって構成されています。
運用スポンサーはInvesco PowerShares Capital Management, LLC、
受託銀行はThe Bank of New York Mellonです。(楽天証券調べ)
基本情報
- 対象指数:ナスダック100指数
- 上場市場:NASDAQ
- 主なセクター:IT、通信、小売、バイオテクノロジーなど
QQQの組入れ上位銘柄(2020年7月1日時点)
QQQの上位組入れ銘柄は、
いわゆる**GAFAM(Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft)**を中心とする
世界的に有名なハイテク企業が多くを占めています。
| 銘柄名 | 保有比率(概算) |
|---|---|
| Apple(AAPL) | 11.86% |
| Microsoft(MSFT) | 11.67% |
| Amazon(AMZN) | 10.79% |
| Facebook(FB) | 4.29% |
| Alphabet(GOOGL) | 3.73% |
| Alphabet(GOOG) | 3.63% |
| Intel(INTC) | 2.39% |
| NVIDIA(NVDA) | 2.25% |
| Netflix(NFLX) | 2.05% |
| Adobe(ADBE) | 2.03% |
※出典:Bloomberg
ご覧の通り、IT・テクノロジーセクター中心の構成となっています。
配当利回りについて
QQQの**直近配当利回りは約0.64%です。
参考までに、VOO(S&P500連動型ETF)は約1.92%**の配当利回りとなっています。
過去の配当実績(1株あたり配当金)は以下の通りです。
| 支払時期 | 配当金額(米ドル) |
|---|---|
| 2020/6 | 0.424 |
| 2020/3 | 0.363 |
| 2019/12 | 0.458 |
| 2019/9 | 0.384 |
| 2019/6 | 0.416 |
| 2019/3 | 0.324 |
配当目的よりもキャピタルゲイン(値上がり益)重視の運用に適した商品といえるでしょう。
QQQを選ぶメリット
メリット1:米国ハイテク企業に集中投資できる
QQQは、
米国を代表する成長企業(Apple、Amazon、Microsoftなど)に効率的に投資できる点が大きな魅力です。
今後も世界経済をけん引するであろうハイテクセクターにまとめて投資できるため、
**中長期のキャピタルゲイン(株価上昇益)**を狙う投資家に適しています。
メリット2:運用コストが比較的低い
QQQの運用コスト(経費率)は、
他のアクティブファンドと比較して割安です。
長期保有を前提とする場合でも、コスト負担が軽減される点は大きなメリットとなります。
QQQのデメリット
デメリット1:セクター集中リスク
QQQは、
- IT
- 通信
- 消費者向けテクノロジー
など、特定業界への集中度が非常に高い構成となっています。
そのため、
IT・ハイテク分野の不調=QQQ全体の下落につながりやすいリスクがあります。
実際、個別銘柄のウェイトも大きいため、
例えばAppleやAmazonが大幅下落すると、QQQ全体に与える影響も大きくなります。
デメリット2:配当利回りが低い
QQQの配当利回りは0.64%程度と、
VOO(S&P500連動型ETF)などと比較してもかなり低めです。
これは、組入れ企業の多くが、
- 低配当
- 無配
であるためであり、
配当収入を重視する投資家には向かない点に注意が必要です。
QQQでは、基本的に**株価の上昇益(キャピタルゲイン)**を狙う運用スタイルが求められます。
森の見解
QQQは、名前も印象的で、
IT・ハイテク好きな私にとって非常に魅力的なETFだと感じました。
ただし、
現在の資金力では購入単価が高く、今すぐには手が出せそうにありません。
今後、資金力に余裕ができたら、
中長期的な成長を見込んでQQQもポートフォリオに加えたいと考えています。