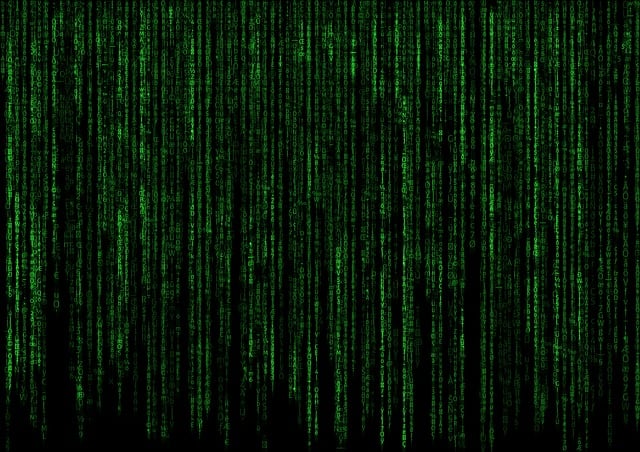C++のswitch文は、ある変数の値に応じて複数の処理を分岐させたい場合に便利な構文です。本記事では、switch文の基本的な使い方と注意点について、サンプルコードとともに丁寧に解説いたします。
目次
サンプルコード(C++)
以下のコードでは、入力された数値に応じて異なるメッセージを表示するswitch文の基本的な構成を紹介しております。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int code;
cout << "コード番号を入力してください。" << endl;
cin >> code;
switch(code) {
case 100:
cout << "コード100が入力されました。" << endl;
break;
case 200:
cout << "コード200が入力されました。" << endl;
break;
default:
cout << "100または200を入力してください。" << endl;
break;
}
return 0;
}
コードの解説
このプログラムでは、次のような処理を行っております。
codeという整数型変数にユーザーからの入力を受け取ります。switch文により、入力された値が100、200、それ以外のいずれであるかを判定します。- 各条件に応じて異なるメッセージを表示します。
break文があることで、該当する処理を実行した後にswitch文から抜けるようになっています。
switch文のポイント
switch文は、**整数値や列挙型(enum)**など、離散的な値の判定に向いています。- 各
caseの末尾にはbreakをつけるのが一般的です。これを省略すると、次のcaseへ**処理がそのまま流れてしまう(フォールスルー)**ため注意が必要です。 defaultは、どのcaseにも該当しなかった場合に実行される処理です。省略することもできますが、エラーメッセージなどを出力したいときに有用です。
if文との使い分け
- 比較演算子(<, >, ==など)を使った複雑な条件判定には
if文が適しています。 - 複数の特定の値に対して処理を分けるような単純な条件分岐には、
switch文の方がコードが簡潔になります。
まとめ
switch文は、変数の値に応じた分岐処理を効率的に記述できる構文です。caseごとに処理を分け、break文で抜けるようにするのが基本です。defaultを活用することで、想定外の入力にも対応できます。
C++の条件分岐を理解するうえで、switch文の役割は重要です。特に「明確な値ごとの処理」が必要な場面では、コードの可読性が向上しますので、ぜひ実践に取り入れてみてください。