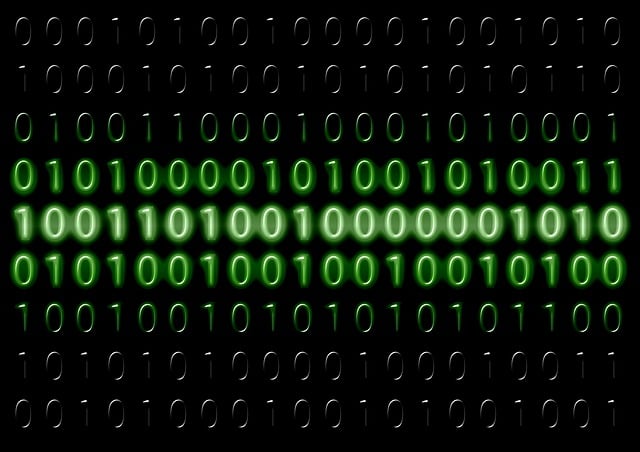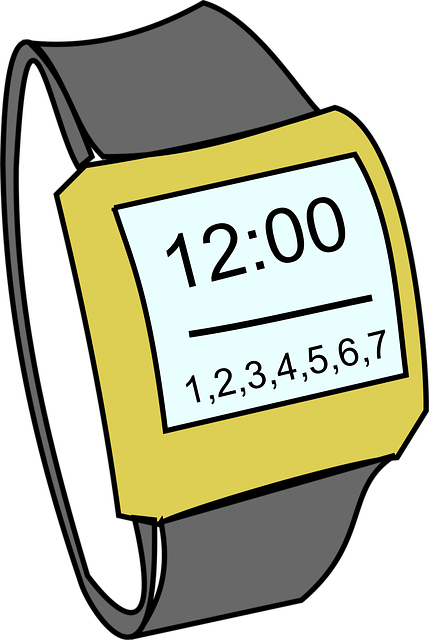Linux環境でテキスト編集を行う際によく登場する「vi(ブイアイ)」と「vim(ヴィム)」ですが、両者の違いをご存知でしょうか。「viとvimは同じもの」と誤解されがちですが、実際には明確な違いが存在します。
本記事では、これからLinuxを学ぶ方やサーバー管理を始めた方に向けて、viとvimの違いを初心者にもわかりやすく、丁寧に解説いたします。
viとは
vi(ブイアイ)は、1970年代後半にUNIXの標準テキストエディタとして誕生しました。その名前は「Visual Editor」の略称で、当時のコマンドライン環境において視覚的な編集を可能にした、画期的なエディタです。
viの特徴
- 軽量で高速
- 最低限の機能に絞られている
- 多くのUNIX系システムで標準搭載
- 操作性はキーボード主体
現在でも多くのLinuxサーバーや組み込み機器に「vi」がインストールされています。ただし、実際には「vi」と入力しても、後述する「vim」が起動する環境も多いため、違いを正しく理解することが重要です。
vimとは
vim(ヴィム)は「Vi IMproved(改善されたvi)」の略で、1991年に登場したviの上位互換エディタです。オリジナルのviに現代的な機能を多数追加し、より快適なテキスト編集を可能にしています。
vimの特徴
- viの操作性を完全に再現
- マルチレベルのUndo(複数段階のやり直し)が可能
- シンタックスハイライト(色分け表示)対応
- スクロールバーやマウス操作(一部環境)
- プラグインによる機能拡張
- GUI版(gvim)も存在
- 多言語対応
Linuxの多くのディストリビューションでは、vi コマンドを実行すると実際には vim が起動する設定になっています。そのため、気付かずにvimを使っている方も少なくありません。
viとvimの違いを比較
| 項目 | vi | vim |
|---|---|---|
| 起源 | UNIX伝統の標準エディタ | viを拡張した改善版 |
| 機能 | 最小限 | 多機能・プラグイン対応 |
| Undo | 1回まで | 複数回可能 |
| 色分け表示 | なし | あり(シンタックスハイライト) |
| マウス操作 | 基本なし | 環境によって可能 |
| 学習コスト | 低め | やや高いが高機能 |
結論:普段使いにはvimがおすすめ
サーバーや組み込み環境など、最小限の機能しか不要な場面ではviが便利です。しかし、プログラミングやスクリプト編集、複雑なファイル操作を快適に行いたい場合は、圧倒的にvimの方が適しています。
特に以下のような方にはvimをおすすめします。
- Linuxでの開発やサーバー運用を行う方
- 色分け表示や高度な編集機能を活用したい方
- viの基本操作に慣れて、さらに快適な環境を求める方
よくある疑問:viと入力するとvimが起動する理由
多くのLinux環境では、vi コマンドが vim へのシンボリックリンク(別名コマンド)として設定されています。これは、互換性を保ちつつ、vimの機能を標準的に使えるようにするための仕組みです。
ご自身の環境で確認するには、以下のコマンドを実行してみてください。
which vi
ls -l $(which vi)実行結果に「vim」や「vim.basic」などが表示されれば、vi は実際には vim の別名であることがわかります。
まとめ
- vi はUNIX伝統の軽量テキストエディタ
- vim はviを大幅に機能拡張した上位互換エディタ
- 多くのLinuxでは
viコマンドが実質vimを呼び出す - プログラミングや快適な編集にはvimが最適
Linux学習やサーバー管理をスムーズに進めるためにも、viとvimの違いを理解し、用途に応じて使い分けましょう。
IT・ガジェット・電子工作の知識をこれひとつで

ここまで読んでいただきありがとうございます。最後に宣伝をさせてください。
PCアプリの操作解説、最新のガジェット情報、そして電子工作の専門書まで。 Kindle Unlimitedなら、あらゆるジャンルのIT・デジタル関連書籍が読み放題です。
「仕事の効率化」から「趣味の深掘り」まで、高価な専門書をわざわざ買わずに、必要な情報をその場で引き出せるのが最大のメリット。 現在は30日間の無料体験や、対象者限定の「3ヶ月499円」プランなどが用意されています。まずはご自身のアカウントでお得なオファーが表示されるかご確認ください。