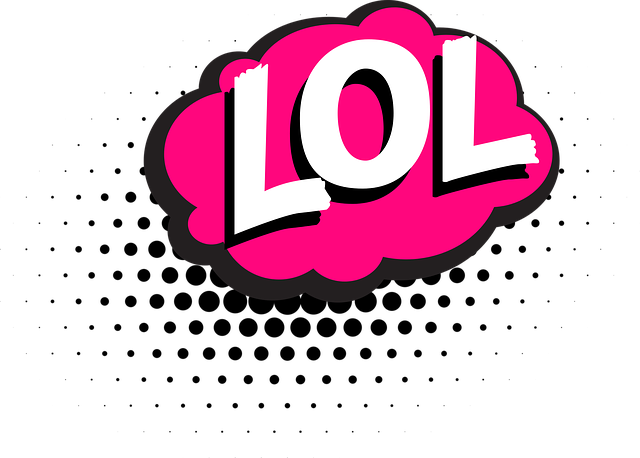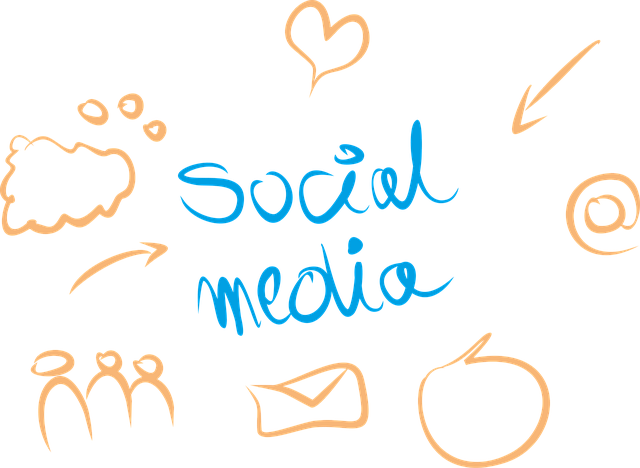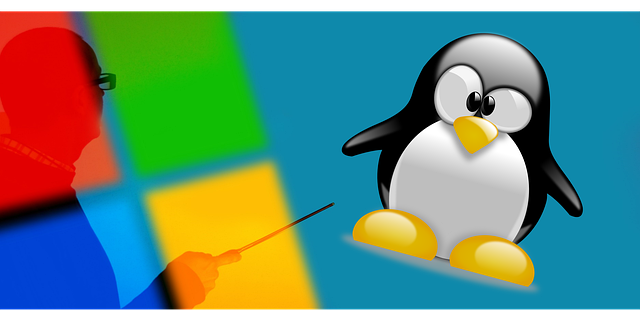LinuxやRaspberry Piなどの環境で作業をしていると、「cat」というコマンドを目にすることがあります。
本記事では、初心者の方にも分かりやすく、catコマンドの意味や使い方を丁寧に解説いたします。
cat コマンドとは?
cat(キャット)コマンドは、LinuxやUnix系のOSにおいて、ファイルの内容を表示したり、複数のファイルを結合したりするためのコマンドです。
もともと「concatenate(連結する)」という英単語から名付けられており、複数のファイルを連続して出力する用途でも使用されますが、**最もよく使われるのは「ファイルの中身を表示する」**という場面です。
基本的な使い方
もっとも基本的な使い方は以下のとおりです。
cat ファイル名たとえば、test.txtというファイルの中身を表示したい場合は、次のように入力します。
cat test.txt
これだけで、ファイルの内容がターミナル画面に表示されます。
実用例:設定ファイルの中身を確認する
Raspberry Piでアクセスポイントを設定する際に使用される hostapd.conf の中身を確認したいときは、次のように入力します。
cat /etc/hostapd/hostapd.conf
このコマンドを実行することで、設定に誤りがないか確認することができます。特にスペルミスや空白行が原因でサービスが起動しない場合など、原因を突き止めるうえで cat は非常に役立ちます。
複数ファイルの表示(連結)にも使える
catは複数のファイルをまとめて表示することも可能です。
cat file1.txt file2.txt
このように書くことで、file1.txtとfile2.txtの内容が続けて表示されます。
注意点
catコマンドは表示専用です。ファイルの編集はできません。- 内容が長すぎるファイルは、一気にスクロールされてしまうため、
lessやmoreなどのコマンドと組み合わせて使うのがおすすめです。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コマンド名 | cat(キャット) |
| 主な用途 | ファイルの中身を表示する、複数ファイルを結合する |
| 利用場面 | 設定ファイルの確認、ログのチェックなど |
cat コマンドは、Linuxにおける最も基本的かつ便利なコマンドのひとつです。
特に設定作業やトラブルシューティングの際には、中身の確認ツールとして欠かせません。
これからLinuxやRaspberry Piを使いこなしていきたい方は、ぜひこの機会にcatの使い方を覚えておきましょう。