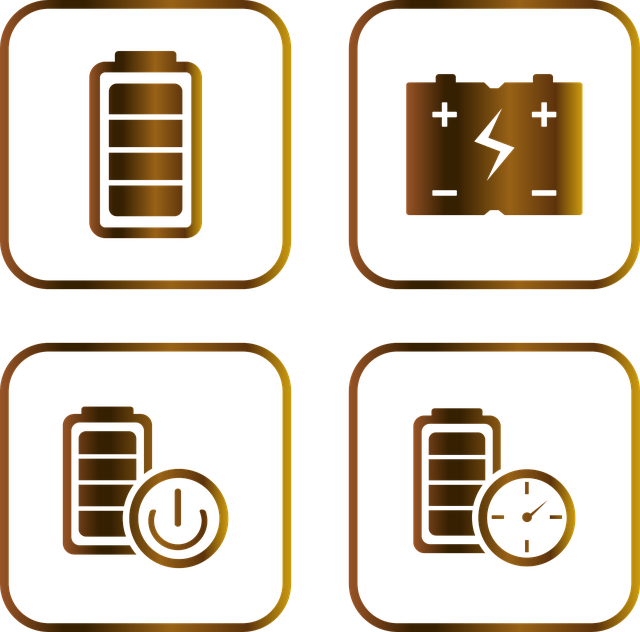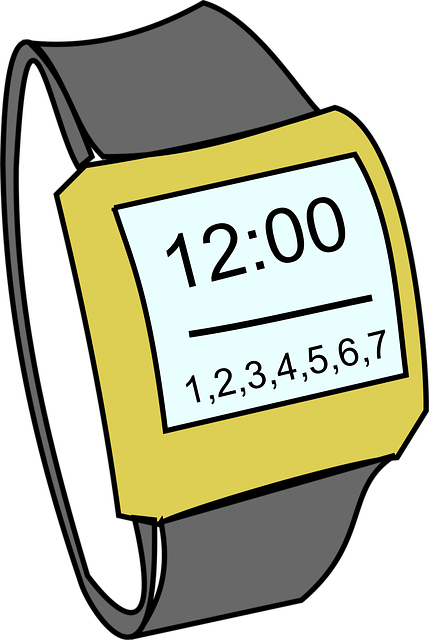電子工作や回路設計を行う際、IC(集積回路)のデータシートとにらめっこする時間は欠かせません。その中で、電源に関するピンとして「VCC」や「GND」はお馴染みですが、時折「VS」というピンが登場し、混乱の原因となることがあります。
「GND, VCC, SCL, SDA」といったピン配列なら、VCCに電源(例えば5V)を接続することは容易に想像できます。
しかし、「RX, VCC, TX, GND, K, VS」といったピン配列の場合、 「VSは12Vなどの主電源に繋ぐのだろうが、ではVCCは何のためにあるのか? どちらも電源ピンのようだが、どう使い分けるのか?」 「VCCは電源『入力』なのか、それともICから5Vが『出力』されるのか?」 といった疑問が生じます。
本記事では、この「VS」と「VCC」の基本的な違いと、それぞれの役割、そして具体的な接続方法について、特に車載インターフェースIC(L9637Dなど)を例に取りながら詳しく解説いたします。
「VS」と「VCC」の基本的な役割の違い
結論から申し上げますと、VSとVCCはどちらも電源ピンですが、その役割と電圧が明確に異なります。
VCC (Voltage at the Collector) – ロジック回路用の安定化電源
- 役割: IC内部のマイコンやロジック回路(頭脳部分)を動作させるための電源です。
- 電圧: 一般的に、3.3Vや5Vといった低電圧で、かつ安定化された(ノイズの少ない)電源を必要とします。
- 由来: 元々はバイポーラトランジスタ(BJT)のコレクタ(Collector)に接続する電圧を意味する記号でした。現在では、MOSFET系(VDD)とほぼ同義で、デジタルICのロジック電源ピンとして広く使われています。
VS (Supply Voltage / Vehicle Supply) – パワー段用の高電圧電源
- 役割: モーターを駆動するドライバ段や、高電圧の通信ライン(K-Lineなど)、アナログ回路といった、**大きな電力や高い電圧を扱う部分(パワー段)**を動作させるための電源です。
- 電圧: 5Vに限りません。例えば車載用ICの場合、車両のバッテリー(12V)に直結されることを想定しており、数Vから数十V(サージ電圧含む)という広い電圧範囲に対応できるよう設計されています。
- 由来: 「供給電圧 (Supply Voltage)」や、特に車載用では「車両電源 (Vehicle Supply)」の略として用いられます。
最大の疑問:「VCC」は入力か?出力か?
この疑問が、VSとVCCを理解する上で最も重要なポイントです。
結論:多くの場合、VSもVCCも「入力」です
「VCC」という名前から、IC内部で生成された5Vが「出力」されるピンではないかと誤解されがちですが、VSとVCCが両方存在するIC(特にインターフェースICなど)において、VCCは「入力」ピンである場合がほとんどです。
- VS (入力): 外部の主電源(例: 12Vバッテリー)から高電圧が入ってきます。
- VCC (入力): 外部の安定化電源(例: 5Vレギュレータ)から低電圧が入ってきます。
もしICが内部にレギュレータを持ち、外部に5Vを供給できる場合は、「VREG」や「VOUT」、「REGOUT」といった別の名前が付けられるのが一般的です。
なぜ電源を2系統に分離するのか?
では、なぜわざわざ2種類の電源を入力する必要があるのでしょうか。これには明確な理由があります。
- ノイズ耐性と保護のため 高電圧側(VS)は、バッテリーの変動やモーターなどから発生するサージ(瞬間的な高電圧)やノイズの影響を直接受けます。もし電源が1系統しかなければ、そのノイズがIC内部のデリケートなロジック回路(頭脳部分)に伝わり、誤動作や破損を引き起こしてしまいます。VSとVCCを物理的に分離することで、高電圧側のノイズからロジック側を保護しています。
- レベル変換を内蔵するため 車載IC(L9637Dなど)を例にすると、VS側(12V系)でK-Lineという高電圧の通信を行い、VCC側(5V系)でマイコン(Arduinoなど)とUARTという低電圧の通信を行います。IC内部でこの「12Vの世界」と「5Vの世界」の信号レベルを安全に相互変換するために、それぞれの基準となる電源(VSとVCC)が必要になります。
- 低消費電力化のため ICのロジック回路は、低い電圧で動作させた方が消費電力を抑えられます。パワー段は高電圧(VS)で動かしつつ、ロジック部は低電圧(VCC)で動かすことで、システム全体の効率を高めています。
具体的な接続例と「よくある疑問」
疑問:「VCC」はArduinoの5Vピンに接続して良いか?
回答:はい、多くの場合で問題ありません。
Arduino UNOやNanoといったボード上の「5V」ピンは、USBや外部電源から生成された安定化された5Vです。これは、ICが要求する「VCC(5Vロジック電源)」の条件に合致します。
接続例(L9637DとArduinoをUSB給電で使う場合)
車両バッテリー 12V→VS (IC)Arduino の 5V ピン→VCC (IC)Arduino の GND ピン→GND (IC)Arduino の GND ピン→車両バッテリーの GND
接続時の注意点
- GND(グラウンド)の共通化 これが最も重要です。ArduinoのGND、ICのGND、そしてVS側の電源(バッテリー)のGNDは、すべて電気的に接続(共通化)してください。GNDレベルが異なると、信号(RX/TXなど)が正しく伝わりません。
- 電流容量の確認 IC自体がVCCで消費する電流は数mA程度と少ないため、Arduinoの5V電源で通常は十分です。しかし、もし同じArduinoの5V電源に、サーボモーターやLEDストリップなど消費電流の大きな部品を多数接続している場合は、ArduinoのレギュレータやUSBポートの電流容量上限を超えないよう注意が必要です。
関連用語のやさしい解説
最後に、今回の説明で登場した関連用語を分かりやすく解説します。
1. 5Vレギュレータ
入力された不安定な電圧(例: 12Vバッテリー)を、安定した出力電圧(例: 5V)に変換(整える)ための電子部品または回路のことです。ICが必要とする「安定した5V」を作り出すために使用されます。
2. 外付け DC-DC / LDO
レギュレータの具体的な種類です。「外付け」とは、ICのパッケージ(黒い樹脂部分)の外部に、ベッド部品として基板上に取り付けることを意味します。
- DC-DC (DC-DCコンバータ): スイッチング方式。電圧を変換する効率が非常に高い(発熱が少ない)のが特長ですが、回路がやや複雑でノイズが出やすい側面もあります。12Vから5Vへの降圧など、入出力の電圧差が大きい場合に適しています。
- LDO (Low Dropout Regulator): リニア方式。電圧差を熱として捨てて電圧を安定させます。回路がシンプルでノイズが少ないのが特長ですが、電圧差が大きいと発熱が大きく効率が悪くなります。
3. 5V ロジック電源
「5Vレギュレータ」によって作られ、ArduinoやICのVCCピンに供給される「安定した5Vの電源系統(配線ライン)」そのものを指す言葉です。
(補足)主な大文字略語一覧
- IC (Integrated Circuit): 集積回路
- VCC (Voltage at the Collector): ロジック回路用電源
- VS (Supply Voltage / Vehicle Supply): パワー段・高電圧用電源
- GND (Ground): 接地、電位の基準点 (0V)
- LDO (Low Dropout Regulator): 低ドロップアウト型リニアレギュレータ
- DC-DC (Direct Current to Direct Current Converter): 直流-直流変換器
- RX (Receive): 受信
- TX (Transmit): 送信
- UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): 非同期シリアル通信
まとめ
電子部品の電源ピン「VS」と「VCC」の違いについて解説いたしました。
- VCC: IC内部のロジック(頭脳)用。安定した低電圧(例: 5V)を入力する。
- VS: IC外部と接続するパワー段(駆動部)用。高電圧(例: 12V)を入力する。
- 分離理由: ノイズからの保護と、異なる電圧レベル間の信号変換のため。
- 接続: Arduinoの5VピンはVCCとして利用可能。ただしGNDの共通化は必須。
最も確実な情報は、使用するICのデータシートに記載されています。「Pin Description(ピン説明)」や「Absolute Maximum Ratings(絶対最大定格)」の項目を必ず確認し、VSとVCCを誤って接続しないよう、安全に電子工作をお楽しみください。
IT・ガジェット・電子工作の知識をこれひとつで

PCアプリの操作解説、最新のガジェット情報、そして電子工作の専門書まで。 Kindle Unlimitedなら、あらゆるジャンルのIT・デジタル関連書籍が読み放題です。
「仕事の効率化」から「趣味の深掘り」まで、高価な専門書をわざわざ買わずに、必要な情報をその場で引き出せるのが最大のメリット。 現在は30日間の無料体験や、対象者限定の「3ヶ月499円」プランなどが用意されています。まずはご自身のアカウントでお得なオファーが表示されるかご確認ください。
ここまで読んでいただきありがとうございます。最後に宣伝をさせてください。