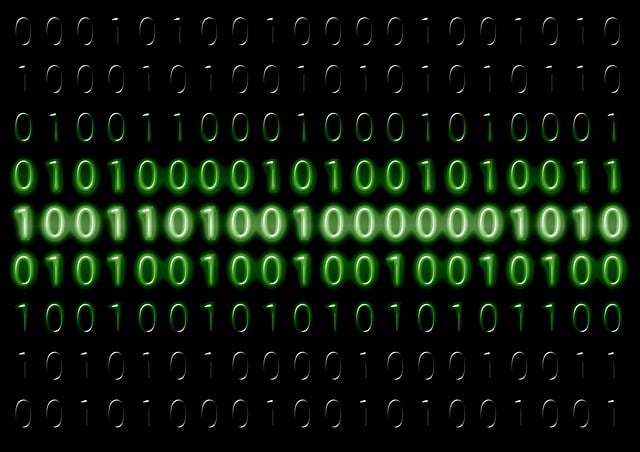本記事では、C++におけるif文の基本的な使い方と、その動作の仕組みについて解説いたします。初心者の方がつまずきやすい「中括弧の省略」による挙動の違いにも焦点を当て、わかりやすく整理しております。
目次
サンプルコード(C++)
以下は、C++のif文の動作を確認するための簡単なサンプルコードです。
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int input;
cout << "数値を入力してください。" << endl;
cin >> input;
if (input == 5)
cout << "5が入力されました。" << endl;
cout << "プログラムを終了します。" << endl;
return 0;
}
コードの解説
このコードでは、次のような処理を行っております。
- ユーザーに数値の入力を促します。
- 入力された数値が5であれば、「5が入力されました。」と表示されます。
if文のブロックには中括弧{}が使用されていないため、ifの条件が真である場合に実行されるのは直後の1行のみです。- 最後のメッセージ「プログラムを終了します。」は、条件にかかわらず常に実行されます。
応用と注意点
中括弧を使わないとどうなるか
初心者が見落としがちですが、if文の条件に合致した場合に実行される文は、1行だけです。次のように複数行の処理を条件付きで行いたい場合は、必ず中括弧{}で囲む必要があります。
if (input == 5) {
cout << "5が入力されました。" << endl;
cout << "条件に合致しています。" << endl;
}
このように記述することで、「inputが5のときだけ、2行分の処理が実行される」という意図を明確にできます。
まとめ
if文は条件に応じて処理を分岐させる基本構文です。- 中括弧を省略した場合、
ifの条件に合致して実行されるのは直後の1文のみとなります。 - 複数の処理をまとめて実行したい場合は、必ず中括弧で囲むようにしましょう。
プログラムの意図しない動作を避けるためにも、初心者のうちは中括弧を明示的に使用することを強くおすすめいたします。