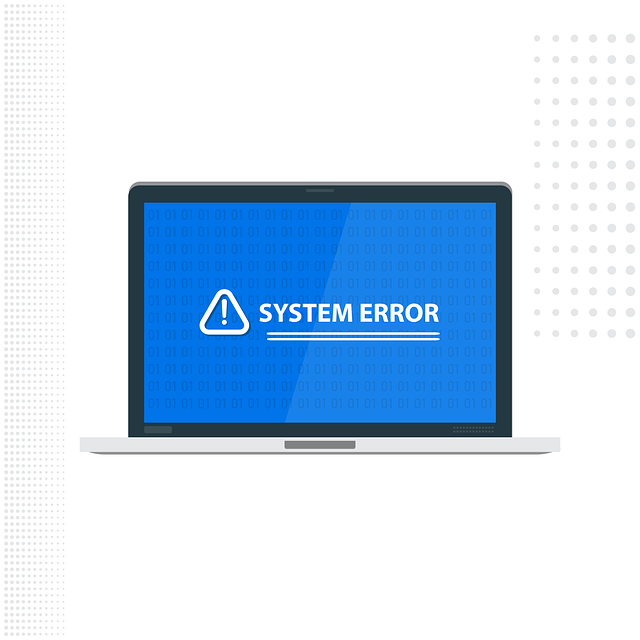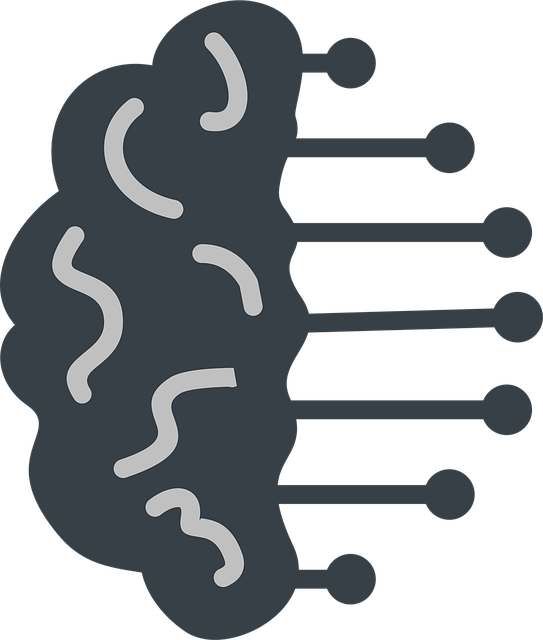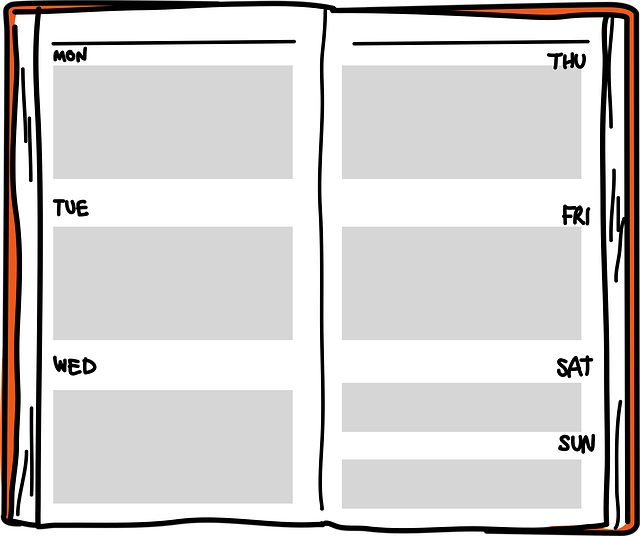Raspberry Pi 5を使って、カメラモジュール(Camera Module V2.1)を接続し、実際に映像を表示するまでの手順をまとめました。Raspberry Pi 5では従来の方法と異なり、設定や使い方にも変化があります。本記事では、RCMBM-SY101-AというV2.1対応カメラを例に、映像表示までの流れを丁寧にご説明いたします。
使用環境と準備
ハードウェア
- Raspberry Pi 5(OS:Raspberry Pi OS Bookworm)
- Camera Module V2.1(型番:RCMBM-SY101-A)
- microSDカード(OSインストール済み)
- モニター、キーボード、マウス、電源、ネットワーク接続(Wi-Fiまたは有線)
ソフトウェア
- Raspberry Pi OS Bookworm(libcamera 対応)
- OSセットアップ済、インターネット接続済
Raspberry Pi 5にカメラを接続する
Raspberry Pi 5には2つのカメラ用コネクタ(CAM0、CAM1)があります。今回のような標準サイズのカメラモジュールはどちらでも使用可能ですが、**CAM1(LANポートに近い側)**の使用が一般的です。
ケーブルの向きに注意
- フラットケーブルのLANポート側に向けて差し込みます。
- 差し込んだ後は、ロックレバーが確実に下りていることを確認してください。
- カメラ側の差し込みも同様に、金属接点がレンズ側にくるように接続します。




カメラ設定は不要(raspi-configでは非表示)
Raspberry Pi OS Bookworm 以降では、カメラの有効化を手動で行う必要はありません。従来は sudo raspi-config にて「Enable Camera」を選択していましたが、現在はlibcameraが標準となっており、設定項目自体が表示されなくなっています。
そのため、カメラを物理的に正しく接続した後、再起動すれば自動的に認識される仕組みとなっています。
カメラが認識されているかを確認する方法
以下のコマンドで、接続されたカメラが正しく認識されているかを確認します。
libcamera-hello正常に接続されていれば、数秒間プレビュー映像が表示されます。
トラブル:カメラが認識されないときの対処法
筆者も初回は以下のようなエラーが発生しました。
ERROR: *** no cameras available ***このエラーは、Raspberry Piがカメラを認識できていない状態です。以下の対応で解決できました。
解決までに行った操作
- カメラの接続状態を確認(向き・差し込みの深さ)
- 一度カメラケーブルを抜き差し
- Raspberry Piを再起動(
sudo reboot) - 再度
libcamera-helloを実行
上記の手順で問題が解決し、無事カメラの映像を表示できました。
おわりに:Raspberry Pi 5でカメラを扱うコツ
Raspberry Pi 5ではlibcameraが標準になり、旧来のraspi-configでの設定が不要となりました。これにより、手軽に高機能なカメラ制御が可能になっています。
トラブルが発生した場合でも、ケーブルの向きや再起動を丁寧に確認することで解決できるケースが多いため、焦らず対処していくことが大切です。
今後はOpenCVによる画像処理や、MJPEG・RTSPなどでのリアルタイム配信といった応用も可能ですので、ぜひご活用ください。
副業から独立まで「稼げる」Webスキルを習得する(PR)
ここまで読んでいただきありがとうございます。 最後に宣伝をさせてください。
「副業を始めたいが、何から手をつければいいかわからない」「独学でスキルはついたが、収益化できていない」という悩みを持つ方には、マンツーマン指導のWebスクール**「メイカラ」**が適しています。
このスクールは、単に技術を教えるだけでなく、**「副業として具体的にどう稼ぐか」**という実務直結のノウハウ提供に特化している点が特徴です。
講師陣は、実際に「副業Webライターから1年で独立して月収100万円」を達成したプロや、現役で利益を出し続けているブロガーなど、確かな実績を持つプレイヤーのみで構成されています。そのため、机上の空論ではない、現場で通用する戦術を学ぶことができます。
副業に特化した強み
- 最短ルートの提示: 未経験からでも実績を出せるよう、マンツーマンで指導。
- AI活用の習得: 副業の時間対効果を最大化するための、正しいAI活用スキルも網羅。
- 案件獲得のチャンス: 運営がWebマーケティング会社であるため、実力次第で社内案件の紹介など、仕事に直結する可能性があります。
受講者の多くは、「在宅でできる仕事を探している」「副業を頑張りたい」という20代・30代・40代が中心です。
受講前には、講師による無料説明が行われます。無理な勧誘はなく、自分に合った副業スタイルやプランを相談できるため、まずは話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。