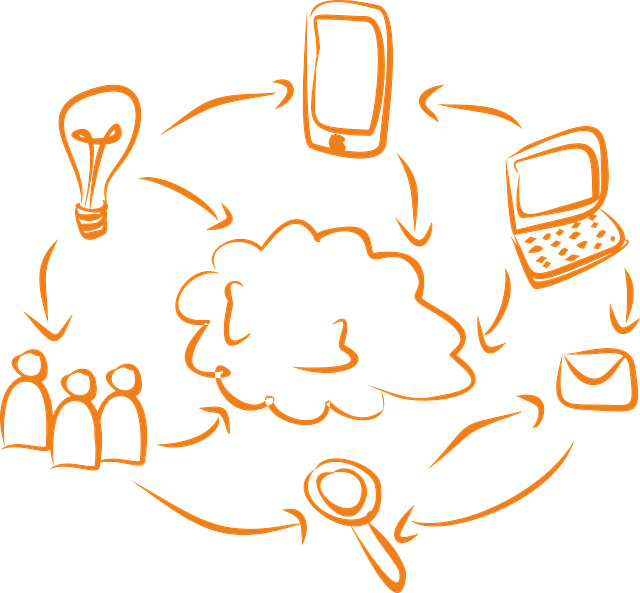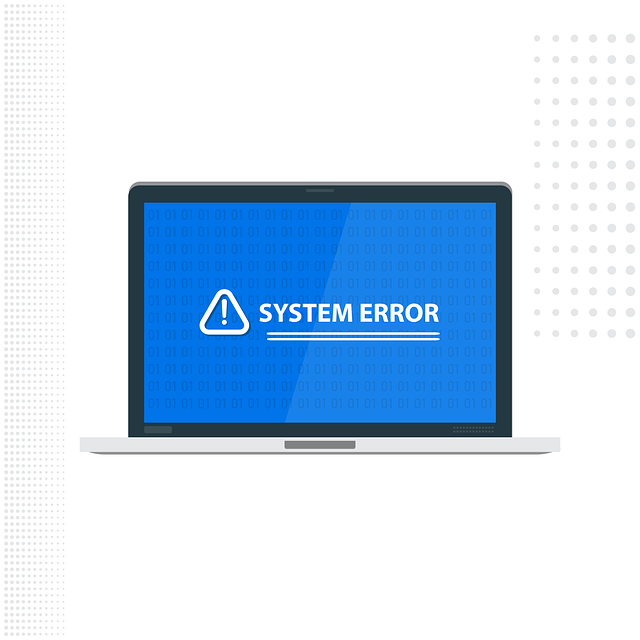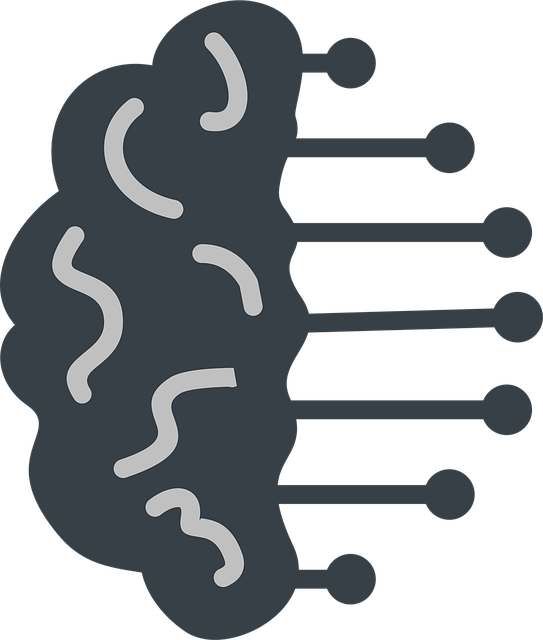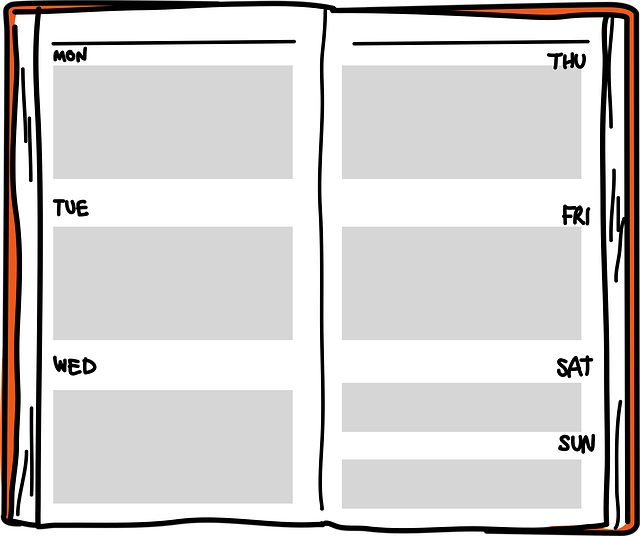家庭や職場で複数のパソコンやスマートフォンを使っていると、「データの保存場所を一元化したい」「どこからでもアクセスできるようにしたい」と感じる場面があるのではないでしょうか。そんなニーズに応えるのが、**NAS(ナス)**と呼ばれる「ネットワーク接続型ストレージ」です。
NASとは?
NASは「Network Attached Storage」の略で、日本語では「ネットワーク接続型ストレージ」と訳されます。簡単に言えば、LAN(ローカルネットワーク)を通じてアクセスできるハードディスクのようなものです。
一般的な外付けHDDやUSBメモリは、一台のパソコンに直接接続して使うものですが、NASはネットワークに接続されているため、複数のデバイスから同時にアクセスすることが可能です。ファイルの保存・共有・バックアップに最適であり、家庭内だけでなく小規模オフィスでも活用されています。
NASの主な特徴
- ネットワーク経由でファイルを共有可能
同じWi-Fiに接続していれば、家族のパソコンやスマホから同じファイルを開くことができます。 - 常時稼働の小型サーバーとして利用可能
内部にはLinuxベースのOSが搭載され、ファイルサーバーやメディアサーバー、クラウド同期機能なども備えています。 - 外出先からもアクセス可能(設定次第)
ルーターの設定やクラウド連携を行えば、インターネット越しにNASへアクセスすることも可能です。
ラズベリーパイで自作NASを構築することも可能
市販のNAS製品も多くありますが、**ラズベリーパイ(Raspberry Pi)**を使って、自分でNASを構築することもできます。たとえば、オープンソースの「Samba(サンバ)」を導入すれば、Windowsと同じようなファイル共有機能を構築可能です。
ラズパイにUSB接続のHDDやSSDを追加し、ネットワーク設定を行うことで、低コストかつ柔軟性のあるオリジナルNASを作ることができます。IT学習やサーバー構築の第一歩としてもおすすめです。
このように、NASはデータ管理や共有を効率化する強力なツールであり、ラズパイの活用によって手軽に構築できる点も大きな魅力です。パソコンやスマホでのデータ整理に悩んでいる方は、ぜひNASの導入を検討されてみてはいかがでしょうか。